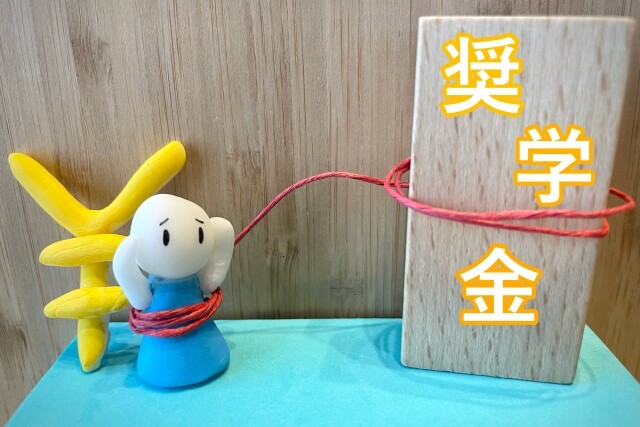- 奨学金の保証人の選び方が分からない
- 奨学金の連帯保証人と保証人の選び方に違いがあるのか分からない
- 後々トラブルにならないように慎重に選びたい
この記事では、このような悩みを解決します。
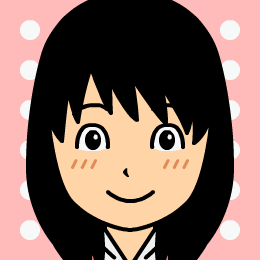
私も奨学金を利用して大学に入学しました。
奨学金を使って大学に通いたい。
けれど、奨学金を利用すると保証人が必要になってきます。
奨学金の保証人をお願いする場合、どんな条件があるのか分からない人も多いのではないでしょうか。
実は、奨学金の保証人を選ぶ時、年齢や収入などの条件があるんです。
なぜなら、奨学金は給付型でない限りは借金をしていることと変わりがないので返済義務があるからなんです。
本記事の内容
- 奨学金の保証人には年齢制限があるってホント!?
- 奨学金の保証人に求められる収入の条件とは?
奨学金には大きく分けて2種類あります。
給付型と貸付型です。
ほとんどの学生さんは貸付型を利用すると思います。
貸付型の奨学金は、将来返済義務があるので、連帯保証人と保証人が必要になってきます。
奨学金は借金と同じなので、後々トラブルにならないよう慎重に選びたいですよね。
そこで対策について調べてみました。
記事の信頼性
- 奨学金受給者は日本学生支援機構( 以下JASSO )に対して保証人を選任することが条件になっている
- 私も奨学金を受給しながら大学に通った
今回は奨学金を受給して大学に通う場合、保証人になる条件や年齢や収入についてご紹介します。
この記事を読み終えると、奨学金の保証人になるための条件や、選び方の注意点などが分かります。
では、早速みていきましょう。
奨学金の保証人には年齢制限があるってホント!?

奨学金の保証人と連帯保証人になるためには、年齢制限があるのはホントです!
【 連帯保証人の年齢制限 】
- 連帯保証人は、貸与終了時に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満
- 保証人は、奨学金の申込日時点で65歳未満
ですので、奨学金を申し込むときに両親が65歳未満でないと申し込むことができないと言う事です。
奨学金を受給しながら大学に通う場合、将来返済の義務がない給付型の奨学金と将来返済の義務がある貸与型の奨学金の2種類あります。
給付型の奨学金は色んな条件があり、その条件を満たしてない限り利用できません。
貸与型は利子のつくものと、利子のつかない奨学金と2種類あります。
どちらの貸与型奨学金も借金と同じですので、JASSOやその他の奨学金でも保証人が必要です。
JASSOを例にとると、奨学金受給者はJASSOに対して保証人を選任し、人的保証制度と機関保証制度のどちらかを選択しなければなりません。
人的保証制度とは、奨学金を受給する奨学生がJASSOの定めている条件を満たした連帯保証人、保証人を選任する制度です。
機関保証制度とは、人的保証制度のような連帯保証人や保証人を必要としない代わりに保証機関が連帯保証を行う制度のことです。
連帯保証人には父か母、または父母に代わる人。
保証人には、4等身以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人が原則です。
例えば、一緒に暮らしていない兄弟や叔父叔母などが保証人になることができます。
奨学金の保証人に求められる収入の条件とは?

保証人になるためには、求められる収入の条件があります。
- 給与所得( 年金含む )が年収320万円以上であるまたは、給与と給与以外の所得が220万円以上
- 預金残高と固定資産税( 土地や住宅 )の評価額を合わせた額が借入額より多い
- 預金残高と評価額/16年と年間収入( 所得 )が320万円以上( 220万円以上 )
このいずれかをクリアしていて、
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 所得証明書
- 年金振込通知書
などの書類を提出できる人が保証人になることが出来ます。
まとめ
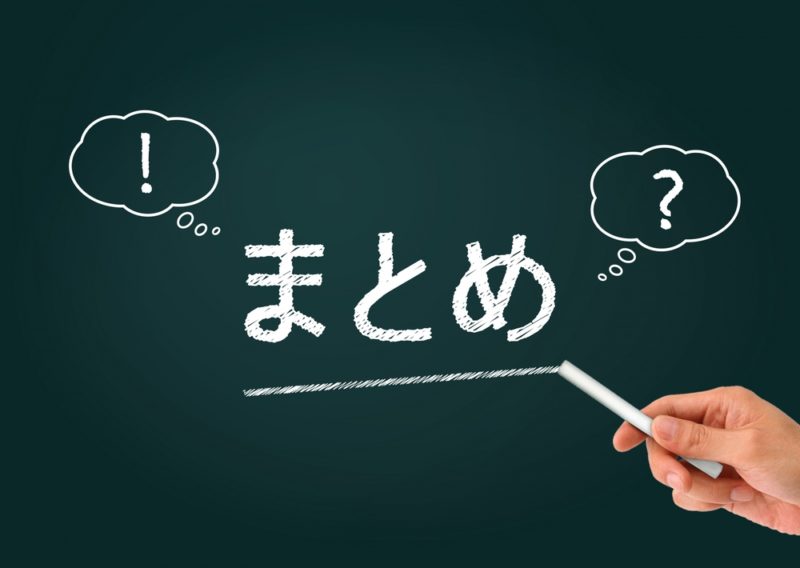
いかがだったでしょうか?
まとめると、
- 保証人の条件は4等身以内の親族の親族の叔父叔母など
- 保証人の年齢は奨学金を申し込むときに65歳未満
- 保証人の収入は給与所得が年収320万円以上か、給与以外の所得が220万円以上
保証人になった場合、責任と義務を負うことになります。
奨学生がきちんと支払えていれば問題はないですが、
返済が滞ってしまったり、何らかの事情で払えなくなってしまった場合は、支払い義務が生じてしまいます。
( 保証人は未返済額の半分、連帯保証人は未返済額の全額 )
後々トラブルにならないよう、慎重に選びましょう。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです(^^♪